こんにちは!総合クリニックで医療事務職員として働いている30代の子育てママ「てりたま」です!医療事務の資格取得や働き方について情報発信をしています。
今回は、医科医療事務と歯科医療事務の違いについて詳しく解説します。さらに、資格取得方法や働く際のポイントもお伝えしますので、「医療事務に興味があるけど、どの分野を目指すか迷っている」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

歯科医療事務の資格取得方法や試験の難易度、資格がなくても働けるかについても解説していきます。歯科医療事務に興味がある方々に役立つ情報を提供していきます。
スポンサーリンク
医科医療事務と歯科医療事務の共通点と違い

医科医療事務と歯科医療事務は、どちらも医療機関での事務的な業務を担当しますが、その内容にはいくつかの共通点と相違点があります。
共通点:
会計業務: 診療費の計算、会計処理、レセプト(診療報酬請求書)の作成。
医療事務用語: 基本的な医療用語や診療報酬に関する知識。

相違点:
専門知識: 歯科医療事務では、歯科治療に関する専門的な知識が必要とされる。例えば、歯科特有の診療報酬や治療内容についての理解が必要。
器具の管理: 歯科医療事務では、歯科治療に使用される器具や材料の管理も重要な業務となる。

医科と歯科の医療事務の違い
| 項目 | 医科医療事務 | 歯科医療事務 |
|---|---|---|
| 診療内容 | 内科・外科など多岐にわたる診療科を扱う | 歯科に特化した診療内容を扱う |
| 専門知識 | 各科の治療や薬の知識が必要 | 歯科治療に関する専門的な知識が必要 |
| 器具の管理 | 基本的に医療事務が行わないことが多い | 歯科治療に使用される器具の管理が重要 |
スポンサーリンク
医科医療事務の資格と取得方法

医科医療事務の資格には以下のようなものがあります。
- 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)
- 医療事務管理士
資格取得には、通信講座や専門学校のカリキュラムを受講し、試験合格が一般的な流れです。通常3~6ヶ月ほどの学習期間が目安です。
スポンサーリンク
歯科医療事務の資格と取得方法
歯科医療事務の資格は、歯科医院での業務を円滑に進めるために必要な知識と技術を持つことを証明するものです。代表的な資格には以下のものがあります。
- 歯科医療事務管理士
- 歯科助手
- 歯科医療事務検定
- 日本歯科医療管理士
これらの資格も、通信講座や専門学校での学習が一般的です。医科と同様に3~6ヶ月の学習期間が目安となります。
日本医療教育財団が認定する資格です。歯科医院での受付業務、会計業務、カルテ管理など、基本的な事務作業に必要な知識を学びます。
日本歯科助手協会が認定する資格です。歯科医師の補助を行うための技術や知識を習得します。患者さんの誘導や器具の準備、清掃など、診療の補助業務を担当します。
全国医療福祉教育協会が主催する検定試験です。歯科医療に関する基本的な知識と、事務処理能力を問う内容となっています。
日本医療教育財団が主催する資格です。歯科医療の管理業務を行うための知識と技術を学びます。事務作業に加え、スタッフの管理や業務の効率化を図るためのスキルも必要とされます。
医科医療事務と歯科医療事務の資格の違い
医科医療事務と歯科医療事務の資格の違いを表にまとめました。
それぞれの資格に必要な知識や取得方法、職務内容の違いを比較していますので、資格取得の参考にしてください。
| 項目 | 医科医療事務 | 歯科医療事務 |
|---|---|---|
| 主な資格名 | 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)、医療事務管理士など | 歯科医療事務管理士、歯科助手など |
| 対象範囲 | 内科、外科、整形外科などの一般診療科目 | 歯科(一般歯科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科など) |
| 資格取得に必要な知識 | 医科レセプトの作成、診療報酬点数表の知識、保険制度、薬や処置の知識 | 歯科レセプトの作成、歯科診療報酬点数表の知識、歯科治療の流れや専門用語 |
| 試験内容 | レセプト作成、診療報酬点数計算、カルテ管理など | 歯科特有のレセプト作成、治療費の計算、歯科器具の取り扱い、診療補助 |
| 取得方法 | 通信教育、専門学校、または資格試験合格 | 通信教育、専門学校、または資格試験合格 |
| 業務内容 | 受付業務、カルテ管理、医科のレセプト作成、請求業務、患者対応 | 歯科レセプト作成、治療費の計算、器具準備、診療補助、患者対応 |
| 必要な期間 | 通常3~6ヶ月程度 | 通常3~6ヶ月程度 |
| 活躍の場 | 病院、クリニック、医療機関全般 | 歯科医院、歯科クリニック |
| キャリアパス | 医療事務主任、病院経営管理、医療クラーク | 歯科助手、歯科衛生士へのキャリアアップが可能 |
| 特有の知識 | 各科の治療や検査、薬の知識、保険制度 | 歯科治療内容(虫歯治療、歯周病ケアなど)、歯科特有の器具や専門用語 |
| 資格の更新 | 必要なし(資格によっては更新や研修が必要な場合もあり) | 必要なし(資格によっては更新や研修が必要な場合もあり) |
スポンサーリンク
歯科医療事務の資格の取り方

歯科医療事務の資格を取得し、仕事に就くためには、いくつかのステップがあります。
一般的な流れは以下の通りです。
学校や講座に通う:
歯科医療事務の専門学校や通信講座で、必要な知識と技術を学びます。多くの学校では、実践的な授業や実習が行われており、現場で役立つスキルを身につけることができます。
資格試験を受験する:
学校や講座での学習を終えた後、各認定機関が主催する資格試験を受験します。試験は筆記試験と実技試験があり、合格すると資格が付与されます。
資格を取得した後は、歯科医院や歯科クリニックでの就職活動を行います。資格を持っていることで、就職活動が有利になることが多いです。
歯科医療事務の試験は難しいのか?
歯科医療事務の試験は、一定の知識と技術が求められるため、決して簡単ではありません。
しかし、しっかりと学習を行い、試験対策を行うことで合格することができます。
試験の内容は、筆記試験と実技試験に分かれており、筆記試験では診療報酬請求事務や医療用語、患者対応に関する問題が出題されます。
実技試験では、カルテの作成や診療報酬の計算、実際の事務作業が評価されます。

歯科医療事務の資格試験に落ちても歯科医院で働くことはできる?
歯科医療事務の資格がなくても、歯科医院で働くことは可能です。
実際、私が知人の歯科医院に話を聞いたところ、「資格よりも人柄やコミュニケーション能力を重視する」との声が多かったです。
ただし、資格があると以下の点でメリットがあります。
- レセプト業務や診療報酬の計算など、専門的な業務を任せてもらえる
- 昇進や給与アップにつながりやすい
- 就職活動でのアピール材料になる
資格がなくても働きながらスキルを身につけ、後から資格を取得する方法もありますね。
スポンサーリンク
私の資格取得体験談
医療事務資格取得のための勉強方法
私が医療事務の資格を取得した際、家事や育児と両立しながら勉強するのがとても大変でした。勉強時間を作り出す事が一番大変だったように思います。
そこで、次の3つの工夫を取り入れたところ、家事と勉強のバランスをとることができるようになりました。
- スキマ時間の活用
- 娘のお昼寝中や、料理の合間にテキストを読む
- 音声教材の活用
- 家事をしながら音声教材を聞いて、医療用語を耳から覚える
- 学習スケジュールの管理
- 1日30分でも毎日続けるようにスケジュールを立てた
この方法で無理なく勉強を続けることができ、無事、試験にも合格することができましたよ。
医療事務に興味を持ったきっかけ
私自身、医療事務に興味を持ったきっかけは「子育てと両立しやすい環境」を知ったことでした。
医療事務の職場は、パートタイムや時短勤務が可能な職場が多いため、子育て中の私にとって魅力的に思えたのです。
医療事務の道に進む際、資格を取得することが非常に難しいと感じ、ハードルは高かったのですが、しっかりと勉強し試験に合格することで、現在の職場でも自信を持って業務を行うことができているため、とても満足しています。
歯科医療事務の資格について
実際の医療現場では、専門知識の重要性を痛感する場面が多々あります。歯科医療事務の資格を取得する際には、歯科ならではの専門用語や治療内容の理解が必要とされます。
また、歯科医療事務は、医科と比べると患者さんとのコミュニケーションがより密接な場面が多く、患者さんの不安を和らげる対応スキルが大切だといわれています。
スポンサーリンク
まとめ
医科医療事務と歯科医療事務には共通点も多いですが、それぞれに必要な知識や業務の違いがあります。
- より幅広い診療科をカバーしたいなら「医科医療事務」
- 患者さんとのコミュニケーションや器具管理に興味があるなら「歯科医療事務」
どちらの資格も、しっかりと準備をすれば合格できます。私自身も子育てをしながら医療事務資格を取得し、今の職場で自信を持って働けるようになりました。
これから資格取得を目指す方も、「育児中だから」と諦めず、少しずつでも学習を進めてみてください。私の経験が、あなたの参考になれば嬉しいです!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
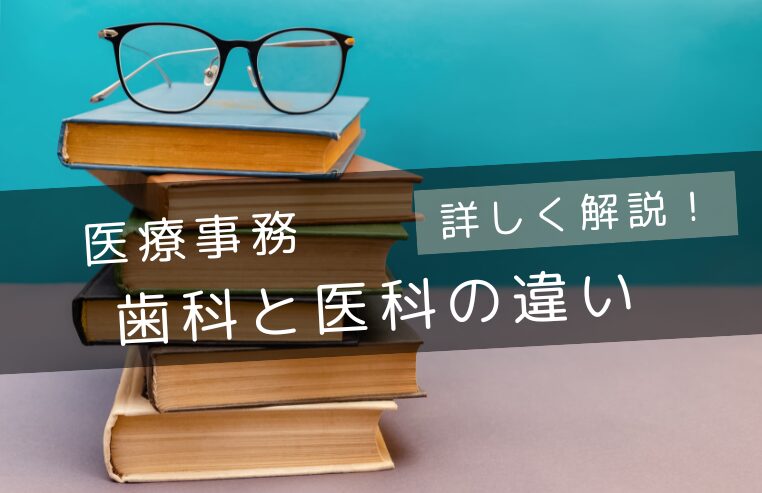
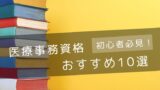

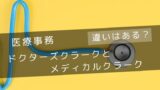
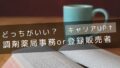

コメント